

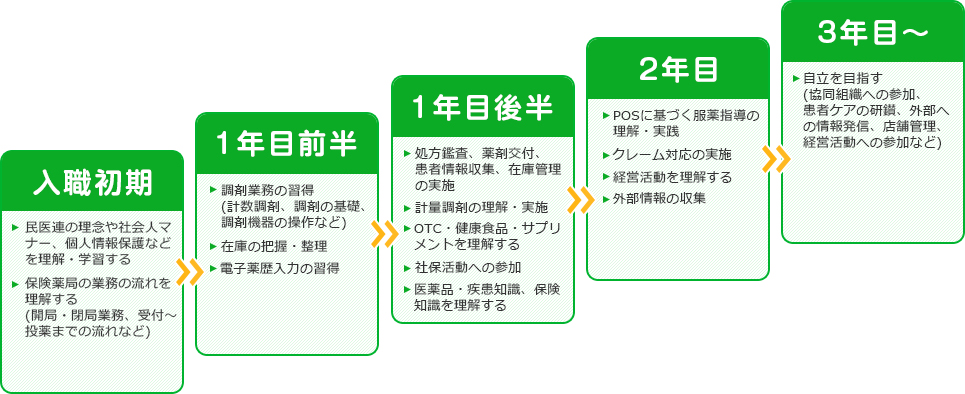
| 大分類 | 小分類 | レベル | 項目点 |
|---|---|---|---|
| 開局・閉局業務 | 開局・閉局業務 | 1 | 調剤機器の立ち上げ、終了、調剤室の片付けができる |
| 1 | 清掃ができる | ||
| 社会人マナー | 社会人マナー | 1 | 服装・頭髪・爪等身だしなみは適切である |
| 1 | 保健衛生と健康管理には留意している | ||
| 1 | 安全性に配慮し、職場の整理整頓・美化に努めている | ||
| 1 | 他の職員に対してきちんと挨拶ができ、言葉遣いが適切である | ||
| 1 | 私語は時と場所を考えるようにしている | ||
| 1 | 諸規定の説明を受け、職員としての権利や義務を理解できる | ||
| 1 | 勤務表に沿って、先輩薬剤師とともに、日常業務が計画的に遂行できる | ||
| 1 | 一つ一つの行為を確認し、納得して業務を行う習慣を身に付ける | ||
| 共同組織 | 共同組織 | 4 | 良くする会や班会などで講師ができる |
| 4 | 班会メニュー作成など主体的に参加できる | ||
| 個人情報保護 | 個人情報保護 | 1 | 個人情報保護に関する基本方針を理解している |
| 1 | 個人情報保護に関する基本方針を遵守し、個人情報の取り扱いに留意している | ||
| 意欲・態度 | 規律性 | 1 | 急な病気・事故による遅刻・欠勤等の連絡が適切にできる(理解している) |
| 1 | 規定の出勤時間、帰社時間が遵守できている | ||
| 1 | 薬局内連絡事項や申し送り事項を把握するように努めている | ||
| 1 | 指示に対する報告は適切になされている | ||
| 1 | 指示は適切に実行できている | ||
| 1 | 決められている事項は遵守している | ||
| 責任性 | 1 | 与えられた仕事は最後までやり終えることができる | |
| 1 | 他に依存することなく自分の責任として取り組むことができる | ||
| 1 | 自分の失敗を周りに転嫁することをしない | ||
| 1 | 仕事の進捗状況や出来映えを常に確認するように努めている | ||
| 1 | 職員としての自覚に欠けることなく取り組むことができる | ||
| 積極性 | 1 | どんな仕事でも引き受け良心的に成し遂げるよう努めている | |
| 1 | 研修会等の会合に出席して発言するよう努めている | ||
| 1 | 仕事に対する改善提案を率先して行うよう努めている | ||
| 1 | 常に問題意識を持ち仕事に取り組むよう努めている | ||
| 1 | 仕事は計画的に段取りよく行うよう努めている | ||
| 協調性 | 1 | 薬局内において他職員と業務上のチームワークがとれている | |
| 1 | 職場行事に参加し、協力している | ||
| 1 | 相手の立場を考えて行動し、信頼を得ている | ||
| 1 | 他の人の仕事を自発的に手伝うように努めている | ||
| 1 | 人の嫌がる仕事でも進んでやるように努めている | ||
| 1 | 勤務時間の変更にも快く応じるように努めている | ||
| 理念 | 理念 | 1 | 民医連綱領と方針を理解している |
| 1 | 薬局の基本方針と医療・福祉宣言を理解している | ||
| 1 | 民医連新聞や「いつでも元気」を読み、問題意識を深めている | ||
| 社保活動 | 社保活動 | 1 | 社会保障制度の充実や平和を守るための各種署名の内容を理解している |
| 2 | 各種署名内容の趣旨を患者様に説明することができる | ||
| 2 | 県内外で行われる社保・平和関係の集会・大会・平和行進などに参加している | ||
| 2 | 患者様の人権や受療権を守る視点を常に心がけている | ||
| 4 | 一部負担金や医療保険制度などについて患者様の相談に応えることができる | ||
| 調剤業務 | 調剤業務 | 1 | 処方箋通り正しく集薬(錠剤・散剤ヒート・外用)ができる |
| 1 | 調剤機器の操作ができる(消耗品交換、掃除など) | ||
| 1 | 調剤内規を理解している | ||
| 1 | 薬袋・ラベルの記載ができる | ||
| 2 | 散剤計量混合が正しく行える | ||
| 2 | 水剤計量混合が正しく行える | ||
| 2 | 軟膏計量混合が正しく行える | ||
| 2 | 予製剤の種類を把握し作成できる | ||
| 2 | 調剤マニュアルを遵守した調剤が身についている | ||
| 2 | 薬剤に関わるインシデントやアクシデントは必ずレポートとして提出できる | ||
| 3 | 患者様に応じた一包化の作成ができる | ||
| 監査 | 監査 | 1 | 麻薬や向精神薬など特殊薬剤に関して、帳簿類への記載が正確にできる |
| 2 | 麻薬や向精神薬など特殊薬剤の処方箋を監査し、記載内容を含めた監査ができる | ||
| 2 | 処方箋の保険法規的監査ができる(医師印、処方箋交付期限等) | ||
| 2 | 用法、用量のチェックが行える | ||
| 2 | 老人・小児の薬用量のチェックが行える | ||
| 2 | 保険日数のチェックが行える | ||
| 2 | 調剤録と処方箋の相違を発見できる(入力ミス) | ||
| 2 | 必要な疑義照会を行うことができる | ||
| 2 | 処方箋の備考欄に必要事項を記載できる(疑義照会) | ||
| 3 | 配合禁忌・相互作用・使用禁忌のチェックが行える | ||
| 3 | 裸錠・ヒートから医薬品を判別できる | ||
| 在庫管理 | 在庫管理 | 2 | 棚卸方法が理解できている |
| 2 | 棚卸を実施することができる | ||
| 2 | 基本的な発注・納品・在庫システムを把握し薬剤師としての日常処理ができる | ||
| 3 | 常に在庫状況に気を配りながら業務が行える | ||
| 患者ケア | 情報収集 | 2 | 患者アンケートの目的を患者様に説明し、記入のお願いができる |
| 2 | 問診表をもとに患者様から基本情報の収集が行える | ||
| 3 | 処方内容から患者様の病態を類推し、かつ病態・ADL等のインタビューを行える | ||
| マナー | 1 | 患者様の来局時や帰られる時に笑顔で挨拶ができる | |
| POS・SOAP | 2 | POSの考え方を理解している | |
| 2 | 患者アンケートによる情報把握ができて初回指導が実施できる | ||
| 2 | 基礎的なコミュニケーション技法を用いることができる | ||
| 2 | 薬歴簿に必要事項をを記入することができる | ||
| 2 | 問題点ごとにSOAPで薬歴を記入できる | ||
| 3 | ①開いた質問、閉じた質問を使い分けることができる(※閉じた質問:「はい」、「いいえ」) | ||
| 3 | ②患者様との会話の中で、効果的な繰り返しができる | ||
| 3 | 意識してコミュニケーション技法を使用している | ||
| 3 | 患者様の問題点を聞き出すことができる | ||
| 3 | 薬歴簿に他の薬剤師が見ても理解しやすい記録が作成できる | ||
| 3 | 薬歴簿の患者情報欄に必要事項を記入することができる | ||
| 3 | 薬歴簿に問題点として必要事項を記載することができる | ||
| 4 | ③患者様との会話の中で、意識的に誉める、認める言葉を使っている | ||
| 4 | ④自分自身のブロッキングに気が付く事ができる | ||
| 4 | 基礎的なコミュニケーション技法は、意識せずとも用いることができる | ||
| 4 | 患者様の感情に着目し、患者様のニーズを探ることができる | ||
| 4 | 患者様の問題点を抽出できる | ||
| 4 | 把握した問題点に対し、薬剤師としての専門性を活かした判断ができる | ||
| 4 | 把握した問題点に対し、適切なケアプランを立てることができる | ||
| 4 | 薬歴簿の問題点リストを活用し、患者ケアに役立てることができる | ||
| 薬剤交付 | 2 | 患者様の名前をフルネームで確認している | |
| 2 | プライバシーに配慮した行動がとれている | ||
| 2 | 患者様にわかりやすい表現で薬品の保存方法、使用法を説明できる | ||
| 3 | 薬剤情報提供文書を適切に使用し、説明することができる | ||
| 4 | 薬剤師から情報発信するなど、医師、看護師との情報共有しながら服薬指導できる | ||
| クレーム | 2 | 各種トラブルに際しては、薬局長・主任などに報告し、その指示に沿って対処できる | |
| 3 | 薬剤師関連法規について理解している | ||
| 3 | 患者様のクレームに対して適切な対応ができる | ||
| 3 | 患者様の電話での問い合わせに対応することができる | ||
| 3 | 発生したクレーム調剤過誤について適切な報告書が作成できる | ||
| 学術力 | 研鑽・情報収集 | 1 | 専門誌を購読している |
| 1 | 必要な専門書等で学習を行っている | ||
| 1 | 薬や医療関連の情報についてアイパッド等を利用することにより注意できている | ||
| 2 | 添付文書の判読ができ、必要な情報を入手できる | ||
| 2 | パソコンなどを利用して医薬品を検索して必要な情報を入手できる | ||
| 3 | 外部団体が主催する研究会・研修会へ参加している | ||
| 3 | 副作用を収集し、薬歴や副作用報告書記載など必要な手続きが取れる | ||
| 3 | 副作用が疑われる場合の可否判断と患者への指導、医師への報告ができる | ||
| 4 | 副作用を調査し、調査表を作成し薬事委員会等に報告できる | ||
| 4 | DSU(医薬品安全対策情報)の意味を理解して活用することができる | ||
| 3 | Word等で文書作成ができる | ||
| 3 | Excelで表計算し簡単な集計ができる | ||
| 医薬品知識 | 1 | 医薬品の配置場所がわかる | |
| 1 | 医薬品の在庫の有無がわかる | ||
| 1 | 医薬品の規格(単位)がわかる | ||
| 2 | 薬品の配置を把握し、有効期限や保管条件を確認することができる | ||
| 2 | おおよそ医薬品の非採用規格がわかる | ||
| 2 | おおよそ医薬品の一般名がわかる | ||
| 2 | おおよそ医薬品の同種同効薬がわかる | ||
| 2 | おおよそ医薬品の禁忌・重篤な副作用は把握している | ||
| 2 | おおよそ医薬品の重要性の高い相互作用は把握している | ||
| 2 | おおよそ医薬品の薬効を患者様に説明できる(大分類程度) | ||
| 2 | おおよそ医薬品の詳しい薬効を患者様に説明できる | ||
| 2 | おおよそ内服薬(錠剤、散剤、液剤)の服用方法、保存方法を患者様に説明できる | ||
| 2 | おおよそ外用剤(眼科用、貼付、軟膏、吸入、坐剤)の使用方法、保存方法を患者様に説明できる | ||
| 2 | おおよそ注射剤の使用方法、保存方法を患者様に説明できる | ||
| 2 | おおよそ小児の服用方法の説明ができる | ||
| 3 | 正確に医薬品の非採用規格がわかる | ||
| 3 | 正確に医薬品の一般名がわかる | ||
| 3 | 正確に医薬品の同種同効薬がわかる | ||
| 3 | 正確に医薬品の禁忌・重篤な副作用は把握している | ||
| 3 | 正確に医薬品の重要性の高い相互作用は把握している | ||
| 3 | 正確に医薬品の薬効を患者様に説明できる(大分類程度) | ||
| 3 | 正確に医薬品の詳しい薬効を患者様に説明できる | ||
| 3 | 正確に内服薬(錠剤、散剤、液剤)の服用方法、保存方法を患者様に説明できる | ||
| 3 | 正確に外用剤(眼科用、貼付、軟膏、吸入、坐剤)の使用方法、保存方法を患者様に説明できる | ||
| 3 | 正確に注射剤の使用方法、保存方法を患者様に説明できる | ||
| 3 | 正確に小児の服用方法の説明ができる | ||
| ジェネリック | 2 | ジェネリック医薬品について患者様に説明できる | |
| 2 | ジェネリック医薬品について患者様に選択・提案ができる | ||
| 疾患知識 | 2 | 基礎的な(代表的な)疾患の知識がある | |
| 3 | 疾患の指標となる検査値の意味がわかり、患者様に説明できる | ||
| OTC・健康食品・サプリメント | OTC・健康食品・サプリメント | 1 | OTC・健康食品・サプリメントの陳列、掃除等に気を配ることができる |
| 2 | 店舗OTC・健康食品・サプリメントの名前がわかる | ||
| 3 | 患者様に商品特徴が説明できる | ||
| 4 | OTC・健康食品・サプリメント全般について患者様の相談に乗ることができる | ||
| 保険請求関連 | 保険知識 | 1 | 医薬分業の歴史と基本的な理念を学ぶ |
| 2 | 処方箋受付からレセプト請求までの一連の流れを理解している | ||
| 2 | 保険薬局と保険薬剤師について理解している | ||
| 2 | 保険種別について理解している | ||
| 3 | 公費負担医療制度・種類について理解している | ||
| 3 | 医療保険による在宅患者訪問薬剤管理指導について概要を理解している | ||
| 3 | 介護保険による居宅療養管理指導について概要を理解している | ||
| 4 | 法別番号と都道府県番号について理解している | ||
| 4 | 介護保険について理解している | ||
| 4 | 生活保護法による医療扶助について理解している | ||
| 4 | 退職者医療制度について理解している | ||
| 4 | 特定疾患と保険について理解している | ||
| 4 | 公害医療・労災保険における保険調剤について理解している | ||
| 調剤報酬・請求 | 2 | 一部負担制について理解している | |
| 3 | 調剤報酬明細書について患者様に説明できる | ||
| 経営活動 | 経営活動 | 1 | コピーや消耗品等の無駄を排し、機器・備品・車両を大切に取り扱うことができる |
| 2 | 薬剤を有効に無駄なく利用する習慣を身に付ける | ||
| 3 | 薬価の仕組みなど薬に「商品」としての側面があることを認識する | ||
| 3 | 経営資料の見方がわかり、経営状況が理解できる | ||
| 4 | 経費削減の具体的提案と実践ができる | ||
| 4 | 服薬指導など収入確保の具体的提案と実践ができる | ||
| 店舗管理 | 店舗管理 | 4 | 薬事法に従って、毒劇薬の管理を行うことができる |
| 4 | 向精神薬の管理を行うことができる | ||
| 4 | 覚醒剤原料の管理を行うことができる | ||
| 4 | 麻薬の管理を行うことができる | ||
| 現金管理 | 現金管理 | 2 | レジの操作と入出金がトラブルなく正確にできる |
| 学生対策 | 学生対策 | 2 | 中・高校生研修で、中・高校生に薬学部を説明し、疑問に答えることができる |
| 3 | 薬学生実習で、他の薬剤師と分担して業務の説明ができる | ||
| 4 | 入職を呼びかけられる |